 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室 旧ヤマジュウ田村家住宅主屋季節展示「くらしのうつりかわりと暖をとる道具展」
2024年1月20日(土)~3月20日(水) 小学生の学習単元に合わせ、生活の変遷を伝える道具と、冬の暮らしを伝える道具の展示を、旧ヤマジュウ田村家住宅の主屋にて行います。 また、桃の節句に合わせ、旧ヤマジュウ田村家住宅に受け継がれてきた...
 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室 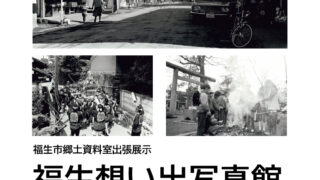 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室 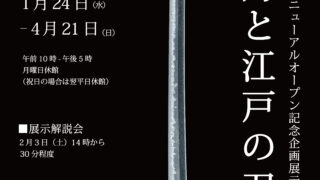 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室 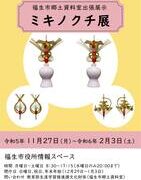 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室 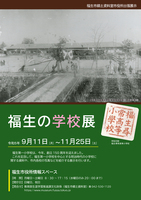 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室 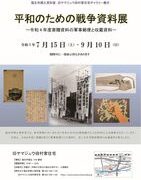 福生市郷土資料室
福生市郷土資料室